
Vol.9
児童生徒と呼ばれる時代に学ぶべきこと
 子供たちの日々の学習に求められているのは何でしょうか?
子供たちの日々の学習に求められているのは何でしょうか?
おそらく「生きる力」なのでしょう。
では、「その具体的なものは何か」と問われたとき、どうのように答えますか。
児童生徒と呼ばれる時代に学ぶべきことは、『自己を向上させるためのワザの獲得』にあると考えています。
例をサッカーにとってみましょう。
あるサッカー好きの少年がポルトガルのエースストライカーのクリスチャン・ロナウドのような速くて低い球を打ちたいと考えました。そこでクリロナのビデオを何度も、しかもコマ送りで繰り返し見ました。
さらにサッカー好きのお兄ちゃんや少年サッカーチームの監督にも質問して、その結果足首の角度と足の振りの速さが必要だとわかりました。そして、自分が納得いくまで毎日毎日繰り返し練習して、クリロナとまではいかなくても今までより速くて低い球を打つことが出来たとします。
このサッカー少年の例でもわかるように、自己が向上するためには、
①やりたいものとやりたい気持ちがある。
②モデルとなるもの、つまりまねるものがある。
③自分の疑問をまとめる力と、それを表現する能力がある。
④単調な繰り返し作業を飽きずに続けられる持続力がある。
⑤一つのことにこだわる集中力がある、と言ったことが重要で、その結果少年は速くて低い球を蹴るワザが習得できたのです。
これを勉強に置き換えてみましょう。
すると、いきなり大きな壁にぶつかります。
「①のやりたいものが勉強にはない。従ってやる気も起こらない」、
さらには「②のまねるモデルがない」と答える子供が圧倒的に多いのではないでしょうか。
スポーツや芸術コースを進む子供でなければ、本当にやりたいことや憧れの人物に出会うことは皆無に近いと思えます。でも、本当に子供たちは、今日の自分より明日の自分が少しでも向上していたいと考えていないのでしょうか。
楽観的かもしれませんが、三十年余り子供に接してきて、そう考えている子供に出会ったことはありません。誰でもが変わりたいのです。
今の自分に満足などしていないのです。昨日の自分よりも今日の自分が、少しでも向上していたいと願っていますし、今日よりも明日の自分が少しでも輝いていたいと考えているはずです。そのことは何も子供に限らないはずです。
ここに自己向上のワザが生まれる基盤があります。自己を向上させたいという思いを叶える具体的な方法を、どうやって子供たちに伝えられるかが、学習塾に関わる者の使命だと考えています。
つまり、勉強することで何が変わるのか、それも頑張って有名大学に入れば上場企業に就職できるといった現世利益としてではなく、自分の内面を変えるために勉強しなければならないことをしっかりと伝える義務があると考えます。
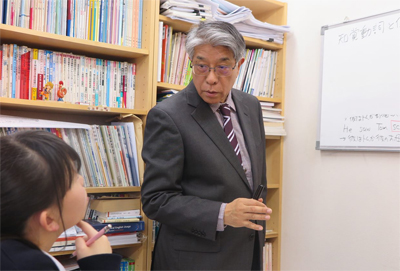
まとめる力が付いてくればノートの書き方が俄然よくなりますし、発言内容も論理的になってきます。集中力が上がってくれば、瞳はきらきらと輝きだしますし、ケアレスミスが圧倒的に減っていきます。こうした内面の変化による外的変化を実感したとき、子供たちは自分が代わってきたことを実感し誇りに思えるのです。
ここに教育をする側の指導という“道(どう)”があると確信しています。
勉強とスポーツは違うという人もいますが、見てきた限りでは何も変わりはありません。今日の自分より、明日は少しだけ違う自分でいたいという熱い思いがあれば、人は変われるのです。
若いころ仕事の壁にぶち当たったとき、ある著名はコンサルタントの先生が「岡田さん、念じ方が足りないからですよ」と助言してくれました。要は、変わりたいという強い思いと単純な繰り返しを確実にやりきる技が足りなかったのです。
大人になって営業マンとして配属され、何で自分だけ売れないのかと悩んだとき、それまでの人生で大きな壁を経験し、しかもその壁を突き破ったことがある人は、何らかの論理的な(感情的でない)方法を確立しようと努めるでしょう。これをもっと突き詰めれば、やる気と単純な作業の繰り返しなのです。
こうした大人としての失敗の中に、子供たちに伝える大切な要素が隠れているのです。
この春、一人でも「自分は変った」と言える生徒を育てていってみたいと思います。
