
Vol.16
これから大学受験を迎える君たちとその保護者にむけて
2.医学部受験に向けて
②今後の対策
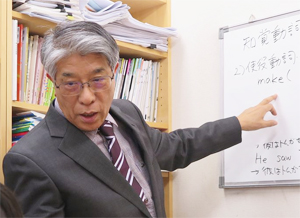 これから医学部を受験する予定の高校生とその保護者は、「共通テスト」対策として今すぐ大学入試センターのホームページからの問題をダウンロードして見ることをお勧めします。
これから医学部を受験する予定の高校生とその保護者は、「共通テスト」対策として今すぐ大学入試センターのホームページからの問題をダウンロードして見ることをお勧めします。
問題文の圧倒的な長さや、教科書には出てこないような題材などを見れば、探求型テストの主旨がよく分かると思います。
80%の壁を越えるためには、どの教科を一番の課題とするかを決めていくことです。
続いて予備校などが主催する模試の活用法について考えてみましょう。
特に医学部受験の場合、各大学の定員が大体100名前後という狭き門のため、模試を受けて自分の学力の客観的な評価を得ることには、受験勉強を進めるうえで大きな意味があります。模試の活用法には、次の3つがあります。
1つ目は、個人成績表の活用です。
たとえば駿台や河合塾のような全国模試の場合、全国・学内での位置を把握するのはもちろんのことですが、設問別成績もじっくりと見ておくことが大切です。
全国平均と見比べながらどこが苦手分野かを確認し、その対策をいつまでにどのようにするかを計画的に進める必要があります。
また、科目別偏差値のグラフから、科目間のバランスを確認することも重要です。特に医学部合格を勝ち取るには、不得意科目を徹底的に鍛え、総合力を引き上げることがいちばんの近道です。
そして、志望大学判定についても細かく見る必要があります。同じB判定でも、A判定に近いのか、C判定に近いのか。あと何点取れば判定が1ランク上がるのか。ライバルと比べた自分の位置を把握し、個人成績表の1ページ目と合わせて判定評価を上げるために必要な課題は何かを書き出していくことです。
2つ目は、採点講評の活用です。
予備校の模試は受験から約1か月後、個人成績表とともに渡される採点講評に、復習時に注意すべきポイントが網羅されています。
模試の直後は「解答・解説」を読みながら復習をすることになると思いますが、約1か月後に返却された自分の答案と照らし合わせながら採点講評を熟読して、再び全体を見直す機会を設けてください。必要な箇所をまとめて自分専用の復習ノートを作っておくのも1つの手です。
そして3つ目は、自己採点の練習としての模試を活用することです。
自己採点の練習は、何度やっても損はないと思います。
曖昧な解答になった場合、自己採点ではどうしても甘くなりがちです。特に「共通テスト」の本番では、こうした自己採点の甘さで、第1段階選抜ラインをクリヤーできない悲劇が毎年のように起きています。
日ごろから細心の注意を払って練習しておきましょう。
何よりも毎回本番のつもりで向き合っていきましょう。
